「特発性血小板減少性紫斑病」についての一見解・仮説
紫斑病といわれる病には、アレルギー性紫斑病の他に、
「特発性血小板減少性紫斑病」
と、呼ばれるものがある。
質問を受ける事があるので、この項では私が考える「見解・仮説」を述べてみたいと思う。
(あくまでここで述べていく内容は、様々な書籍・先生方の教えに加え、私の経験・考えを加えまとめたものであり、全ての術者が同じ考え方を持っているわけではないことを、念のため付け加えておく。)
現代西洋医学においてメカニズム・治療法が明確でない病だが、簡単に言えば、
「血液を固める血小板の数が減ってしまい、皮下出血を引き起こすもの」
と、考えられているようだ。
そのため、アレルギー性紫斑病とは別の、「特発性血小板減少性紫斑病」と呼ばれているのだが、「特発性」とは「原因不明」という意味で、
「原因が分からないが、数値的に血小板の減少が見られるため起こる病では?」
と、言っているに過ぎない。
現代西洋医学での見解
現代西洋医学では、
「原因が特定できないが、なんらかの理由で血小板数が減少してしまう事により、出血しやすくなる病気」
と、いう見解である事はすでに述べた。
ここで言う「なんらかの理由」というのは、
「血小板に対する自己抗体ができ、この自己抗体により脾臓などで血小板が破壊されるために、血小板の数が減ってしまう」
などと推定されているが、これは根本原因への説明になっていない。
仮に自己抗体が絡んでいるとしても、「なぜ自己抗体ができるのか」が根本原因であるはずだ。だが、未だ明確な事は分かっていないのだから、当然治療法も定まっていない。
ちなみに、血小板が減少する疾患は色々とあるが、その大まかな区分として、
A:産生能力の低下(血小板を造る力の低下)=「造る量が減る」
B:血小板寿命の低下(血小板を使いすぎる、血小板が造られても破壊されてしまう)=「使いすぎ・造っても壊しすぎる」
が、考えられる。
それに照らし合わせてみると、先ほどの自己抗体によって血小板が破壊される説は②を指しているわけだが、あくまで現代西洋医学において明確な事は分かっていない。
ここで「血小板」について少し触れておきたい。
血小板とは、血液に含まれる細胞成分の一種であり、血管壁が損傷した際には、傷口を塞ぎ、止血する役目を果たす。
つまり、簡潔に言えば、
「血を固める事」
が、血小板の存在理由である。
現代西洋医学では、血小板・白血球・赤血球など全ての血球は、「骨髄」において造血幹細胞から分化すると言われている。血小板産生後にはその三分の一が脾臓に分布し、8~12日で老化した血小板は主に脾臓などで破壊されるとされる。
この血小板の数が減ると出血しやすく、さらに出血が止まりにくくなるため、紫斑や出血症状(便尿に血が混じる、鼻・歯茎・口の粘膜出血など)が出てくる。
血小板は、1マイクロリットルあたりおよそ15万~35万個程度が基準値とされており、血小板数が10万個以下となる状態を「血小板減少症」と呼び、40万個以上となる状態を「血小板増多症」と呼ぶ。
つまり、「特発性血小板減少性紫斑病」とは、「血小板減少症」の一種であるといえるだろう。
10万個以下になると出血が止まりにくくなり、5万個を切ると自然に鼻血が出たり皮下出血が始まって紫色の斑点が出たりするようになる。
3万個以下では腸内出血や血尿、2万個以下になると生命も危険になるといわれ、血小板数が3000を切るような症例では、頭蓋内出血の危険があり早急に治療が必要であるとされている。
血小板減少性紫斑病への処置としては、ステロイドを使用して、血小板数や症状を見ながら徐々に減量していく事を考える場合が多いようだ。
ただステロイドは強烈な副作用もあり、手術で脾臓を摘出する事もあるという。
(つまり、血小板を破壊する役割の脾臓を取り去る事で、血小板現象を防ごうという対処療法の極み。脾臓を摘出しても、血小板数が10万個以上を維持できるようになる場合と、うまくいかない場合があるらしい。)
一説によると、急性型は半年以内に90%以上が自然治癒するとも言われ、慢性型の一部ではピロリ菌の除去を行う事で血小板数が増えるケースもあるらしく、この方法を第一選択に考えるケースが増えてきているようだ。
ただ、ピロリ菌を除去しても無効なケースもあり、3万個以上なら経過観察、2万個以下ならステロイド・脾臓摘出へと移っていくのが一つの目安らしい。
(もちろん担当ドクターの判断によって、それぞれの処置や方針は異なるだろうが。)
小児では大部分が急性型であり、6ヶ月位までに血小板数が自然に正常数値へと戻ることが多く、慢性型に移行するものは10%程度といわれる。
成人慢性型では、ステロイドを減量すると血小板数が減少してしまいやすいため、長期のステロイド治療が必要と判断される場合がある。
ちなみに、血小板数が3万個以上を維持できれば、致命的な出血によって死亡する例は稀だといわれる。
以上、諸説あるが、これらが私の把握するおおまかな西洋医学的見解である。
現代西洋医学理論への一考察
ここで私の見解・仮説を述べる前に、この西洋医学的理論に対しての考察をしておきたい。
繰り返すが、現代西洋医学では、血小板減少性紫斑病について、
「何らかの原因で血小板が減少し、出血症状が出やすくなる」
と、捉えており、血小板減少の理由について、
「血小板への自己抗体ができるため、血小板を排除すべきものとみなし、脾臓などで壊してしまう」
と、考えている。
この考え方によると、出血(紫斑)が生じる流れとして、
①何らかの原因
↓
↓(=血小板への自己抗体をつくる)
↓
②血小板減少(脾臓などでの血小板破壊亢進)
↓
↓
↓
③出血(紫斑)
と、いう風なプロセスとなる。
ただ、ここでいう「自己抗体をつくる」事は、「何らかの原因」そのものではない。
「何らかの原因」の結果として自己抗体が生じ血小板が減少するとしても、あくまでプロセスの中で生じてきたものであり、現代西洋医学ではその根本原因が分からない(故に「特発性」と銘打っている)と言っているのである。
また、脾臓を摘出する事についても、あくまで、
「血小板を破壊している場所が脾臓だ」
と、いう理由で行われる処置であるのだが、脾臓もまた「何らかの原因」には当たらない。
このやり方は、例えれば火事が起こって、それを知らせようと警報ベルが鳴っている時に、本来なら火を消せばベルはおのずと消えるにも関わらず、
「うるさいベルを壊してしまえ」
「鼓膜を取り除きベルが聞こえないようにしよう」
と、するようなものだ。
ステロイドの治療も、火を消すのではなく、あくまでベルに耳栓をする方法である。(それも大いに毒性があるため危険である。)
当然、自然に火が消えてくれない限り、原因が放置したままの火事はますます燃え広がり、ベルはますます激しく鳴り響くことになる。これが対処療法の姿なのだ。
ピロリ菌除去については後述するが、対処療法の域を出ない点は同じである。
要するに、西洋医学における処置のいずれもが枝葉に対するものに過ぎず、「何らかの原因」が掴めないため根幹を放置し、その後のプロセスで「症状を抑えようという試み」がされているだけなのだ。
これは、耳栓をしている間に、自然に火が消えるのを祈っているようなものだ。
自然療法・東洋医学的見解
では、私の見解・仮説を述べていく。
「仮説」と強調する理由は、自然療法においても未だ明確でない要素があるためである。
例えば無痛整体の取り組みにおいて血小板減少性紫斑病が回復した例は存在するが、どのような機序で回復へ至っているのかについては、アレルギー性紫斑病ほどの明確な根拠がないのが現状なのだ。
施術方法の基本スタンスについては変わらないため、自律神経と内臓の働きが大きく関わっている事は間違いないのだが、回復に向かう理由については幾つかの可能性があるとしか現段階では言えない。
それを踏まえたうえで、
「こういう考え方もあるのか」
と、いうスタンスを以て、本項を参考材料の一つとして捉えていただきたい。
まず大前提として、
「症状というのは、体が治そうとするために起こす生理反応であり、メッセージでもある」
と、いう視点が重要となる。
炎症や皮膚症状の本質が、
「体内浄化環境をクリアにするための反応」
「状況を変えて欲しいというメッセージ」
である以上、「皮下出血」もまた同様の意味を持っていると考えるのが自然であろう。
そして、ここが大事なポイントなのだが、
「血小板の減少はあくまで体内浄化のために起こる一現象であり、老廃物をきれいにするためにやむなく体が起こしている反応ではないか?」
「現状の生き方に問題があるため、改善すべきだと知らせてくれているのではないか?」
と、いう仮説を立ててみる事にする。
前述したように、西洋医学的な見解で、血小板減少が起こるケースとして、
A:「造る量が減る」
B:「使いすぎ・造っても壊しすぎる」
のどちらかに当てはまると述べたが、これらを踏まえて、
「何かしらの原因とは?」について考察していきたい。
【仮説① 体内の老廃物を処理すべく血管外への出血反応を起こす場合、血小板の存在が一時的に邪魔になる】
血液の老廃物を処理するのは、便・尿・呼吸・汗・肝臓・腎臓・免疫細胞らであり、内臓の働きが低下するとこれらの働きに多大な影響を与える。
そして、体内浄化環境が悪化すると、老廃物が全身の大切な細胞や器官に蔓延してしまい、悪い影響を及ぼしてしまうため、それを防ぐべく、「生命維持の危機」と判断した体は、何らかの緊急処置を講じてこれを食い止めようとする。
例えば、皮膚から蕁麻疹・できもの・アトピーとして老廃物を外に追い出そうとしたり、咳として出そうとしたりする。
あるいは、菌やウィルスを招き入れて炎症として老廃物を燃やす。
また、症状として外に出せないと、今度は体内に溜める形で血栓(血管内でのブロック)やガン(一箇所に悪いものを固めてしまうフィルター)を形成する。
「出血」として血管外に出す事もまた、その一環である。(ここまではアレルギー性紫斑病の機序と同じ。)
ただ、この時、血小板があると血を固めてしまうため、出血作業がしにくい。
そのため、体は出血作業を進めるために、
「血を固める血小板を一時的に減らす必要がある。そのためには、あえて血小板に対する自己抗体をつくり、脾臓で破壊せねばならない」
と、命令を下す場合があるのではないか?
これこそが、血小板減少が起こる「何らかの理由」の一つではないかと、私は考えている。これは前述した「B:造っても壊し過ぎる」に当てはまる。
もしくは、体は水面下で、
「血小板産生量を減らせ」
と、いう命令までも、出しているのかもしれない。これは「A:造る量が減る」に当てはまる。
つまり、血小板減少性紫斑病とは、「出血してしまう病気」というよりも、
「老廃物を処理したいため、浄化作用の反応としてあえて出血を起こしている」
と、捉える事ができるのではないか? あくまでも仮説であるが。
【仮説② 自律神経の乱れは、骨髄を支える内臓の働きを抑制するので、血小板産生が低下する】
「ストレスで胃潰瘍になる」
など、自律神経と内臓の働きが密接である事はよく知られている。
そして、内臓の働きは免疫・回復力・細胞交換と大きく関わる。
現代西洋医学では、血小板など全ての血球は「骨髄」で造られると言われるが、骨髄といえども細胞であり、細胞の交換は内臓が弱ってしまっては活発さを失う。
つまり、
「自律神経の乱れによって内臓の働きが弱ると、骨髄の血小板産生にも大きく影響してくるのでは?」
と、考える事ができる。
もう少し言えば、表面に出てきた紫斑は、「問題(自律神経の乱れ)を何とかして欲しい」というメッセージの役目をも帯びていると解釈する事ができる。
【仮説③ 筋緊張が骨格構造に影響し、緊張の圧力が内臓や骨髄の働きに負担をかけ、血小板産生の低下を生む】
骨髄は骨の中に存在している。現代西洋医学では、造血機能のある赤色骨髄は、成人になると腸骨・胸骨に多く残るとされる。
その中でも、骨盤(腸骨など)や大腿骨はとても大きな骨であるため、骨髄もそれだけ多い事になる。
仮に、腰背部・股関節・骨盤周りの筋緊張が増した場合、血小板を産生する骨髄とそれを支える内臓への圧迫を生じさせるため、血小板への影響が出やすくなるのではないか?
この仮説を簡単にまとめると、次のような流れとなる。
「ストレス・飲食・疲労の蓄積など日常の生活の乱れ」
「過去の強い怪我や衝撃による体の緊張・ゆがみ」
↓
↓(=自律神経の乱れ、心身の過緊張が生じる)
↓
「筋緊張が骨格構造に負担をかける」
↓
↓
「内臓・骨髄の働きを抑制する」
↓
↓(=細胞産生・細胞交換・免疫・回復力の働き低下)
↓
「血小板減少」
そうなると、
「血小板が減ってしまうのは、筋緊張によって血小板産生をやりにくくしてしまっているためで、特に腰背部・骨盤周りの筋緊張を解くことで戻っていくのではないか?」
と、いう仮説が成り立つ。
そしてこれもまた、紫斑を通じて、「問題を改善して欲しい」というシグナルを発していると捉える事もできる。
そのメッセージを受け止め、筋緊張を解消し、自律神経を安定させ、日常の改善も行い、内臓・骨髄の働きを平常に戻してやれば、血小板減少は回復に向かう事になる。
【仮説④ 「千島・森下学説」における「腸管造血説」「細胞化逆説」を根拠として、内臓の働きそのものが血小板産生に関わる】
この仮説は、従来の西洋医学理論である、
「すべての血球は骨髄で産生される」
と、いう「骨髄造血」を否定するもので、「千島・森下学説」を根拠とする。
この学説は、故・千島喜久男博士が提唱し、森下敬一博士が実証を重ねた理論である。
ちなみにこの学説は、五十年以上も前に発表されながら、これまでの学説を覆す内容であったため、学界から黙殺され続けているが、実に理に適ったものといえる。
ここでは、いくつかある理論の中から、次の二説について簡潔に記しておく。
●「腸管造血説」・・・食(栄養源)は、腸で血(血球細胞)となり、全身を巡って肉(体細胞)となるというもの。
●「細胞化逆説」・・・肉は血となり食となる。飢餓・ケガ・治癒などの事態に遭遇した場合、体細胞は血球細胞に戻り、さらに栄養源に戻るというもの。
つまり、「食物―血球細胞―幹細胞―体細胞」が、互いに変化しあう流れである。
例えば、飢餓状態に陥ると、肉や脂肪などの体細胞は血球細胞に戻り、さらに栄養源となって消費されるために、体はやせ細る。これが細胞化逆である。
この説の裏付けとなるのが、「カントンの犬」と呼ばれる実験である。
フランスの学者であるルネ・カントンは、犬の血液を海水と入れ替える実験を行った。
海水は血液の塩分濃度に調整され、大量の血を抜かれた犬に注入された。
現代西洋医学の常識から考えれば、
「たちまちにして犬は死んでしまうはずだ」
と、思うだろうが、犬は最初ぐったりとしていたものの、やがて元気を取り戻し、実験前より活発に動き回ったという。
この注入された薄い海水には、水とミネラルが含まれているだけで、当然ながら血球成分は存在していない。
だが、血を抜かれた犬の体は、注入された水とミネラルを活用して体細胞を血球細胞に戻し、再び血を造ったのだ。
ただ、カントンの理論も「千島・森下学説」も、現代医学・医療利権によって弾圧・黙殺・隠蔽され、いまだに西洋医学では、
「血は骨で造られる」
「体細胞は血球細胞に戻らない」
と、いう考えのみが定着し続けている。
<参考文献>
『STAP細胞の正体 「再生医療は幻想だ」 復活!千島・森下学説』
(船瀬俊介著 森下敬一監修 花伝社)
『血液の闇』
(船瀬俊介 内海聡著 三五館)
私の仮説②③では、西洋医学の定説である「骨髄造血」に基づき、
「内臓の働きによる支え→骨髄による血小板産生」
と、いう流れを前提とする仮説を挙げた。
だが、今回の仮説④では、「千島・森下学説」の「腸管造血説」「細胞化逆説」を根拠として、
「内臓の働きが血小板産生に直結する。それ故、内臓機能が低下すると血球産生力もまた低下する。そのため一時的に血小板数が減り、出血を起こす事がある」
「ただし、血小板が減少しても、体は体細胞を血球細胞に戻すため、再び血小板数は元に戻っていく」
と、いう考えを提示しておきたい。
(急性型で、90%以上がおよそ半年ほどで自然治癒するのは、こうした理由によるのではなかろうか。)
これは、ストレスなどで内臓の働きが低下したり、飲食の乱れなどで老廃物が蓄積し内臓の浄化排泄機能が疲弊する事で、
「内臓の働きの低下=腸管造血の低下」
↓
↓
「血球細胞産生力の低下」
↓
↓(=血小板減少)
↓
「出血(紫斑)」
↓
↓
「体細胞を血球細胞に戻す=細胞化逆の働き」
↓
↓(=血小板増加)
↓
「出血が止まる」
の流れが生じるという仮説である。
もちろんこれも、紫斑症状を通じて、「問題(内臓の働きの低下)を起こしている状況を変えてほしい」というメッセージであるわけで、無痛整体などを通じて回復していく機序は次のようになる。
「飲食・ストレス解消・施術などで内臓の働きを助け、さらに体内浄化環境を正常化していけば、内臓の働きの向上・負担軽減と共に血球産生力も上向くため、血小板が増え出血反応は止まっていく=腸管造血を助ける」
「あるいは、体がこの事態に対し、体細胞を血球細胞へと戻す事で、血小板数が正常に戻り、自然治癒していく。食改善や施術などはその働きをフォローする=細胞化逆が起こる」
ちなみに東洋医学では、
「気(生命活動のエネルギー)・血(体を栄養する)・津液(体を潤す水分)・精(体を構成し生命活動を維持する物質)は一定の条件下で相互に転化し、精は気と血に転化し、津液と気は相互に転化し、気は血を化生する」
と、言われている。
気・血・津液が全身滞りなく過不足なく巡っていれば健康であると東洋医学では考え、それぞれが滞ると、「気滞」「湿痰」「瘀血」という病理産物が生じ、体に様々な悪影響を及ぼす。
(本書で言う「自律神経の乱れ」や「老廃物・毒素」に当たる。)
さらに、
「気・血・津液・精の生成と補充は、すべて水穀の精微と外界からの清気が原料になっている」
「気の生成には脾・肺・腎が、血の生成には脾・肺・心・腎が、精の補充には五臓全てが関与している」
と、考えられ、血の生成についても、
「飲食物が脾胃の運化(内臓の消化吸収)を受けて水穀の精微(栄養分)に転化した後、営気によって脈中に滲注し、肺に上輸されて清気と合すると共に心火(心陽)の温煦を受けて赤く変化し、血となる」
「腎陽の温煦により腎精が血に転化して脈中に入る」
と、いう機序がある。
東洋医学理論は分かりにくく、荒唐無稽なもののように思われるが、要するに、
「食から得た栄養は、内臓の働きによって血や生命維持のための物質となっていく」
「生命維持のための物質もまた血へと転化する」
と、いう事であり、「腸管造血説」「細胞化逆説」と重なるところがある。
例えば、漢方では出血した患者に対し、人参湯(脾胃の働きを高める)を飲ませる場合がある。
(もちろんきちんとした病態把握に基づいた上での話だが。ちなみに東洋医学で言うこの「脾」という臓腑は、西洋医学で言うところの「脾臓」ではなく、消化器系の働きなどを主り、物質代謝・運輸など生命活動の礎となるため、大変重要である。)
これは、血を造る中心が脾胃の働きであるためで、脾気を高める事が造血に繋がるのである。
まさに、腸管造血の考え方とよく似ている。
脾は気血の生成にも関わるのだが、加えて「統血作用」と言って血管外に血を漏らさぬようにする働きがある。
つまり、脾の働きが低下すると出血する事があるわけで、血小板減少性紫斑病における仮説の一つとして「内臓の働きの低下」が挙げられる事とも符合してくる。
以上が、自然療法・東洋医学的視点から見た血小板減少性紫斑病への私の見解・仮説である。
血小板減少が起こるケースとして、
A:「造る量が減る」
B:「使いすぎ・造っても壊しすぎる」
と、いういずれかに当てはまると述べたが、これを今回の仮説に当てはめると、
仮説①は「造っても壊しすぎる」あるいは「造る量が減る」で、
仮説②③④は「造る量が減る」だといえる。
無痛整体で体の調整を行った結果、血小板減少性紫斑病が回復していくケースがあるのは、これらの要素をトータルでカバー出来ているからだと推量できる。
仮説①なら、内臓処理能力を向上させる事で、自浄作用が高まる。
仮説②なら、自律神経を安定させ、内臓機能のフォローを行う。
仮説③なら、筋緊張解消による内臓・骨髄への負担軽減。
仮説④なら、内臓の働きを高める事で、「腸管造血」を活性化し、「細胞化逆」をサポートする。
いずれも無痛整体で効果が期待できる範疇であり、これらは仮説であるものの、実際に血小板減少性紫斑病が回復した症例が存在する事はその裏付けの一つとなるのではないか。
ただし、注意しておかねばならないのは、
「病の段階がどれほどの重さか」
と、いう点である。
激しい血小板減少が起こっている場合、出血が止まらなくなったり、重篤なケースになる可能性もあるので、ドクターと患者さんとの慎重なやり取りが必要となってくる。
ちなみに血小板数値は、内臓の働きや自律神経の安定によって、老廃物が処理されたり、内臓・骨髄への圧迫が解消されたり、腸管造血・細胞化逆が進んでいく段階で、次第に戻ってくるのではないかと推測される。
例えば、西洋医学的には、小児の場合6ヶ月以内で治まるケースが多いとされ、それ以上は慢性期に入ってくるとされる。
6ヶ月で治まるのは、自浄作用・負担・血小板産生がある程度安定したので治まってくるからだと考えられるし、慢性型になるのはそれらが適わぬ時であろう。
うまくいかないのは、浄化環境の乱れ・自律神経の乱れ・筋緊張・内臓の働きの低下などがよほど著しいからだと思われ、さらにはクスリの長期服用による内臓への負担が大きいのかもしれない。
(クスリで出血を抑えている間に自浄作用・治癒力が働けばいいのだが、浄化排泄に蓋をしたりクスリの毒性の影響もあるため、状況は改善どころか悪化する可能性がある。)
西洋医学的治療法には、「ステロイド」「脾臓摘出」「ピロリ菌除去」らがあるが、いずれも対処療法に過ぎない。
ステロイドや脾臓摘出についてはすでに述べたが、ピロリ菌除去に関しても私の一見解がある。(「こういう考え方もあるのか」という程度に聞いていただきたい。
そもそも菌というものは、キレイな水の中に入れても何ら動きを見せないが、汚い水の中に入れると餌を得た菌は活発に分解活動を始める。
「炎症とは菌の力を借りて老廃物を燃やす反応である」
と、述べてきたが、それは胃に炎症を起こすといわれるピロリ菌にもあてはまる。
体内浄化環境が悪いからピロリ菌が活発に働き炎症を起こすわけで、炎症の根本原因は菌そのものではなく老廃物の蓄積にあるのだ。
つまり、ピロリ菌が増えるから炎症やガンが起こるのではなく、
「浄化環境が悪いから菌が増えるのを受け入れて燃やそうとしたり、燃やしきれない老廃物を全身に蔓延させぬよう一か所に固めるべく体はフィルター(ガン)を形成する」
と、いうメカニズムなのだ。
ガンの転移とは、一か所では止めきれない老廃物を、別の場所にフィルターを作る事で防ごうとする反応といえる。
そのような事が体内で起こっているのに、胃炎やガンの人を検査をして、
「胃にピロリ菌がたくさんいます。だから病気になったのです」」
と、診立てるのは、どうにもピントがずれているように思えてならない。
しかも、クスリで除去しようとすれば、菌が耐性を持ってしまったり、副作用の問題もある。
仮に、ピロリ菌除去によって胃の炎症が抑えられたとしても、肝心の体内浄化環境はそのままであり、体は老廃物の蔓延を防ぐべく別の形で処理しようと、何らかの症状を起こす可能性がある。
これは、花粉症の原因が体内浄化環境にあるのに、花粉のみを防ごうと四苦八苦する姿とよく似ている。
老廃物を溜め込んだ体が、
「これ以上、余計なものを入れてほしくない」
と、花粉などの異物に敏感になっているのが花粉症のメカニズムであり、花粉そのものは根本原因ではないのだ。
くしゃみなどは老廃物排泄の反応であり、浄化環境がキレイであれば起こる理由はないし、花粉が入ってきても過剰反応は起こらない。
同様に、ピロリ菌もまた、炎症を起こす因子の一つに過ぎず、根本原因は体内浄化環境の乱れにあるのだ。
体内浄化を行った結果、血小板数も正常化し、ピロリ菌の活動も沈静化するのなら話は分かる。
だが、浄化環境に目を向けず、ただ菌のみを除去しても、血小板数に変化が無いのはむしろ当然ではなかろうか。
一部でピロリ菌の除去により血小板が増えるケースがあるのは、(あくまで推測だが)別の要因があると考える事もできる。
私の仮説を元に考えれば、そもそも自然治癒力が働き、ある程度の浄化・負担の解消・内臓機能の回復が進めば、血小板減少はストップするはずなのだ。
急性型の9割以上が半年ほどで自然治癒するのはそのためで、本来なら血小板減少は体が起こす一時的な緊急処置に過ぎないのではないかと私は思うのだ。
そう考えると、少々強引に推論を立ててしまえば、ピロリ菌除去と血小板増加に因果関係はほとんど無いのかもしれないし、また、検査を受けるたびに食事制限をする事で図らずしてデトックスが進んだり、検査そのものにも誤差が生じている可能性はゼロとは言い切れないだろう。
人によっては病気になって食生活・生き方を変えた人もいるのかもしれないが、病院でそういった事を考慮する事は稀であり、
「ピロリ菌を除去したら数値が変わった」
と、しか捉えないだろう。
人間の体は、日々流動的に変化し続けている。そして、病院の検査結果もまた、様々な因子により幅が出てくるケースがある。血圧一つ見ても、計り方・計る人・感情の状態・温度や環境の違いなどによって、同じ人物、同じ日付であっても違いが生じる事は容易に想像できるだろう。
画像診断や血液数値などは、判断材料の一つにはなるが、必ずしもそれらだけで体の全てが分かるわけではないのだ。
なぜ、このように言ってしまえるのかというと、
元来、西洋医学のクスリというもの本質は、「治すため」のものではなく、「症状を抑える・ぼやかすため」のものだからだ。
(もっと言えば、西洋医学のクスリとは本来毒そのものであり、効能・作用というのはその副産物に過ぎない。副作用とはむしろ毒の本質そのものである。)
そもそも、ピロリ菌と血小板減少との関連性について、明確に断言できる根拠はどこにあるのか。
「自己抗体によって血小板が破壊されるので脾臓摘出を行えばどうか」
と、いう理屈と、
「ピロリ菌を除去すると血小板が増えるのでは」
と、いう理屈との因果関係など証明しようがないと私は思う。たとえ証明したところで、どれほどの意味を持つというのか。
なぜなら、そのいずれもが根本治療の本質からかけ離れた議論だからだ。
うるさいベルを聞こえなくするのに、
「鼓膜を破るべきか」
「ベルを壊すべきか」
を論じたところで、根本の火事を消す事には繋がらないのだ。
先ほど例に挙げた花粉症で言えば、食べ物やストレスを改善し、必要なら適切な代替医療のサポートを受けるだけで、ほとんどのケースで症状は出なくなる。少々出たとしてもひどくはならない。
なぜなら、「体内浄化環境が改善し、排泄すべき老廃物がある程度処理された」、あるいはそれと共に「体の過剰な防衛反応が解除され、花粉に対する拒否反応が消えた」からだ。
それに反して、症状を抑えたり、花粉を排除する事ばかりに終始するのは、本来おかしい事なのだ。
火を消そうともせず、火がある事にも気付かず、ひたすらうるさいベル音を聞こえなくする事に必死になるのが、現代西洋医学の姿である。
花粉症も紫斑病も同じである。
警報ベルが鳴っている本当の理由を見ようともせず、
「ステロイドで抑えろ」
「脾臓を摘出しろ」
「ピロリ菌を除け」
と、対処療法に走る事のおかしさが分かるだろう。
それで良くなったという人もいるのかもしれないが、うまくいかなかった人もいるわけで、
「脾臓まで取ったのに・・・、一体何だったんだ」
と、悔やんだとしても、
「ガイドラインに沿って最善を尽くした」
と、主張するドクターが罰せられる事はまず無いだろう。
血液製剤(ガンマグロブリン剤)のリスク
また、血小板減少性紫斑病における病院の治療として、免疫グロブリン療法(ガンマグロブリン剤の点滴)を行うケースもあるようだ。
免疫グロブリン(すなわち抗体のこと)製剤とは、人体の血液中に含まれる免疫グロブリンG(IgG)というたんぱく質を高純度に精製・濃縮した製剤で、様々な抗体を幅広く有する「免疫グロブリン製剤」と、特定の病原体に対する抗体を多く含む血漿から造られる「特殊免疫(高度免疫)グロブリン製剤」に分けられる。
病院では、感染症や免疫低下の場合に、血液製剤(ガンマグロブリン剤)を用いようとすることがあるようで、現代西洋医学的説明を簡単にまとめると、
「免疫グロブリン製剤は、血小板を破壊する細胞の働きを抑え、血小板と反応する自己抗体を減らすことにより、血小板を増やす効果があるとされる。効果は一時的で根本治療にはならないが、ステロイドと同様、即効性があるという。成人の場合、急ぎ血小板数を増やしたい場合(重篤な出血や手術前、分娩前など)に限り使用される。小児の場合、重篤な出血は発症初期に起こることが多いことから、できるだけ早く血小板を安全域にまで増やす目的で、血小板減少が著しい例には免疫グロブリン療法がおこなわれる。ひとつの基準を挙げると、免疫グロブリン製剤は通常1日に体重1キロあたり200から400mg/kgほどを5日間連日点滴静注する」
と、いうことらしい。
ただ、血液製剤には様々な問題が存在し、特に輸血には以下のようなリスクがある。
①輸血血液中のリンパ球が生き残っていると、患者の体を攻撃する副作用(GVHD)が起こる可能性がある
つまり、輸血とは一種の臓器移植であり、輸血血液と患者の血液がケンカする事があるのだ。これを発症するとまず助からない。
だが、患者が輸血によって死んでも、医療過誤死を報告しないケースも多く、あるいは知識がないため、
「懸命に治療を行い最善を尽くしたが、病には勝てなかった」
と、関連性にすら気付かず、病気や事故の悪化として処理される事が多々あるのだ。これを発症すると出血が止まらなくなるため、さらに医者は輸血をしようとして、悪循環のループに陥る。
②GVHD防止のため放射線照射を行う事のリスクがある
この時の放射線はとてつもなく高い数値であり、その猛毒を照射された血を体内に入れる危険性は言うまでもないだろう。
「でも輸血したらヘモグロビン値が上がるではないか」
と、言うかもしれないが、輸血で一時的にヘモグロビン値が上がっても、それは見かけの濃度が上がった事によって測定器の数値が上昇した(血の色の濃さで推定計測する仕組み)に過ぎない。
「放射線で死に絶えた血球」を入れても血球は働かないため、「実際のヘモグロビンの働き」が上がったわけではないのだ。
それ故、一時的に数値が上がっても、しばらくすれば放射線で死んだ血球は老廃物として処理されてしまい(それも体にとって負担になる)、また数値が下がるため、再び輸血を勧められてしまう。
さらに、放射線は血小板を破壊してしまうため、その血液は凝固しづらく、そんな血を体内に入れればますます出血しやすくなるのは道理であろう。
③抗凝固剤が入っているため、出血しやすくなる
血小板の働きで血液が固まってしまえば注射針が詰まるため、固まりにくくするためのクスリが添加される。すると、出血しやすいクスリが混じったものを出血している患者の体内に入れるため、ますます出血が止まらなくなるのだ。
その他にも、エイズ・肝炎らウィルス感染のリスク、輸血関連急性肺障害、溶血反応、アナフィラキシーなど、様々な副作用・害のリスクがある。
「でも、出血したら血を入れないとだめじゃないの?」
と、思われるかもしれないが、実は「水分と電解質(ミネラル分)」を入れれば、体は新たな血球を造り、血液となっていくのだ。
この電解質液とは、医療現場で見かける「リンゲル液」や、より人間の電解質バランス濃度に近いものとして「カントン・プラズマ(薄めた海水から精製された代替血漿)」がある。これらを使えば完璧とまでは言い切れないが、少なくともリスクの多い輸血を行うよりは遥かに良い。
輸血して助かったように見える人の実態は、血であるからではなく、水分とミネラルが補給されたからに過ぎない。リスクのある輸血で副作用が出なかった人は、実は幸運であったのだ。
さらにこれらの様々なリスクに加え、ガンなどの治療に輸血が必要ないと主張する理由は、
「輸血をすると免疫が下がり、ガン悪化のリスクが高まる」
からである。
家族の血だろうと、同じ血液型であろうと、指紋と同様に完璧に一致する血液など存在しない。つまり輸血をすると、体は異物の侵入と判断するのだ。
異物が入ってくると、体はなんとかそれを調整しようと働くため、免疫を自ら下げる。(臓器移植で免疫抑制剤を使うのと同じで、それを体が自動的に行う。これができないとGVHDになる。)
免疫が下がれば、ガン細胞はますます大きくなるという理屈である。
これは他の疾患においても同様であり、免疫が下がってしまえば治るものも治りにくくなるのが道理だ。
国内外では、この輸血のリスクを知って、無輸血でのオペを行う医師も増えてきている。
国内のガンで死亡したおよそ8割は、三大療法(手術、抗がん剤、放射線。この中に輸血の害も含まれる)によって死んでいるという戦慄の事態が起こっているのだ。(『血液の闇』 船瀬俊介 内海聡著 三五館)
内海聡医師は、輸血の有害無益性を訴える中で、免疫補助剤などのガンマグロブリン製剤なども同様に無益だと言い切られる。
免疫グロブリン製剤の副作用には、ショック、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、無菌性髄膜炎、急性腎不全、血小板減少、肺水腫、悪心、嘔気、皮疹、悪寒、発熱、頭痛などの報告がなされているが、この中に血小板減少が含まれているのに注目しておくべきだろう。
血小板減少のため製剤を用いているのに、副作用として血小板減少の可能性があるというのだ!
この方法の矛盾さが読み取れるだろう。
これらの副作用は要するに、異物である血液製剤が体内に入る事で、ショックを起こしたり、免疫が下がったりするために起こるものといえる。
体内の免疫が下がったり、体内浄化環境の乱れが起こる事で、肝臓や腎臓など解毒に関わる臓器への負担が増したり、炎症による浄化反応が起こったり、さらには出血という形で排除するための血小板減少、あるいは内臓の働きが落ちることで血小板産生力の低下などを引き起こすと考えられる。
また、血液製剤であるため、ウィルス混入、感染症伝播のリスクを完全排除できない。
西洋医学の矛盾と自然療法・東洋医学の可能性
では、なぜ医者はこのような処置をしようとするのか?
それは教科書やガイドラインに書いてあるからだ。
だが、それらが根本的にずれているのだから、おかしなことになる。
医者は自身が最先端のことをしているつもりだから、自分でおかしいと考えようとしないし、教科書的な見方から離れられない傾向が強い。
体内浄化環境という視点などに触れるはずもなく、「血小板減少という謎の難病」ということで、教科書に従いあれこれと順番に手段を講じていく。
それの原因をほとんど追求しようともせず、ひたすら対症療法に走るのである。
それがクスリやワクチン、日常の食などによって起こっているなどとは思いもしない。
いや、ワクチンなどの副作用群にそうした疾患が含まれていることくらいは知っているだろうが、あえて言及するケースは少ないのではないか?
なぜなら、それを病院が認めたとき、責任問題になりかねないからだ。
ゆえに、そうした指摘をせず、「原因の良く分からない難病」というくくりで患者側を納得させようとし、自身をもごまかそうとする。 心ある医師はそうした問題に向き合おうとするし、そういう視点を持って活動されている方もおられるが、ほんの一部に過ぎない。
医師がこの状態だから、マスコミや教育もその延長線上の情報を垂れ流す。一般市民はそれを善と思い、病院にすべてを丸投げしてしまう・・・。
結果、病院や製薬メーカーは儲かり、患者の心身は損なわれていく。
これは紫斑病に限らず、抗がん剤や向精神薬などで顕著にみられる状況だ。
血小板減少性紫斑病などという病名をつけられたところで、ほとんど現代西洋医学では根本療法に結び付く処置はできないわけで、さらにステロイドやら脾臓摘出やら免疫グロブリン療法やらで体へのリスクを増加させることばかりする。
必ずしも副作用など目に見えた害が生じるとは限らないが(無いならそれはとても幸運であったというべき)、そうした可能性が大いにあるのは事実であり、少なくともそのリスクの数々を患者の多くは知らないはずだ。
そして、現代西洋医学に身を預け丸投げしてしまうのだが、行われるのはリスクがついてまわる対処療法のみである。
このことは、火事が起こっているのに、原因の火を消さず、耳栓をとっかえひっかえしたり、ベルを壊したり鼓膜を取ったりしているようなものだ。
もちろん出血の状況が悪化せぬよう注意深く経過観察をしておく必要はあるだろうが、誤解を恐れずに言えば、かえって何も処置せず放っておいた方がマシなのではないかとすら思えてならない。
なぜなら、小児型の多くの場合、半年ほどで80~90%くらいが自然治癒しているという話があるのだから。
むしろ、残りの10~20%ほどは、いじくりまわした挙句、かえって慢性化している可能性があるのだ。
耳栓をしている間に自然治癒してくれればいいが、大抵の場合、原因である体内浄化環境などをほったらかし、あれこれとクスリなどでいじくりまわしてしまうため、かえって毒を体内に入れてしまい、ますます状況が悪化し、火は燃え広がる。
小児で慢性化する10~20%には、おそらくそうした背景があるのではないか?
この場合、火が出る状況とは、体内浄化環境の悪化を意味し、老廃物や毒素を体内に蓄積するような環境下にあればあるほど、血小板数値を体はあえて下げて出血を起こし、浄化しようとするのだ。
あるいは、内臓の働きが衰え、血小板産生能力が低下するのかもしれない。
いずれにせよ、自律神経を安定させ、内臓の働きを整えていくことで、そして浄化環境を乱さない環境を作る事で、治癒力は発揮される。
つまり、血小板産生能力の回復、あるいは血小板数をあえて減らす命令が解除され、正常化していくのだ。
その方法論とは、体内の毒素排出を助けるような食改善であったり、添加物やクスリなど人工物の侵入を減らしていくアプローチであったりする。
無痛整体などの施術はそうした浄化環境改善をフォローする一助の立場であるに過ぎず、大切なのは原因を見極め、治癒力を引き出すための取り組みなのだ。
それゆえ、重篤な場合を除けば必ずしも医療に頼る必然性は本来なく、自身の治癒力を引き出す環境を整えていけば、自ずと改善していくと私は考えている。必要なら心身に負担のない代替医療などのサポートを最小限求めればいい。
クスリなどで人為的にいじくりまわすほど、慢性化していきやすくなるだろう。
(もちろん、こうした考えはあくまで私個人の物であり、強制するつもりはない。西洋医学での治療を受ける事もまた、各自の自由であり選択なのだ。)
成人型が慢性化しやすいのは、ある意味で大人は子供より複雑な状況(長年の蓄積など)で体内浄化環境が悪くなっており、さらに治癒力も低下しているからだと思う。
そしてそのほとんどの要因は、ストレス、クスリやワクチンの毒性、人口添加物や動物性食品などに問題がある。
だから、体内の解毒を行うような環境改善に取り組む必要があるはずだ。
にも関わらず、毒であるクスリを用いようとするため、用いるほどかえって体内浄化環境は悪化していく。ステロイドなどはじめの強烈な耳栓効果に期待しているうちに、どんどん悪化してしまうケースがあるのだ。
ベル音に蓋をしている間に治癒力が回復し治ってくれればよいのだが、多くの場合、浄化環境が悪化していくのでベル音はますます大きくなる。結果、さらにクスリが増していくという悪循環に陥りやすい。
あくまでこれらは私の個人的な見解であるが。
紫斑病のタイプの違いについて
また、「アレルギー性紫斑病」と「血小板減少性紫斑病」を対比してみると、術者としての立場から次のような推論が挙げられる。
共に施術時は「自律神経と内臓の働き」を調整する事で回復に向かうよう働きかけるのだが、血小板減少性紫斑病は、より「内臓の働き・下半身の筋緊張」が中心な印象を受ける。
前述したように、血小板産生に内臓・骨髄(大きな骨である腸骨や大腿骨に多く含まれる)が関与するとすれば、腰背部や骨盤周りへのアプローチを行うことで内臓・骨髄の働きを助ける事が血小板減少に対するサポートになるのだと思われる。
もちろんこれは一つの指標であり、各自の体を確認しながら施術を行うのが基本スタンスである事に変わりはない。
仮説の域を出ないが、アレルギー性紫斑病は「首」つまり「上」にメインの緊張が強い人が発症しやすいのではないか(首は自律神経と深く関わるため、アレルギー的な反応、敏感な警戒反応が出やすい)。
一方、血小板減少性紫斑病は「腰背部・骨盤周り」つまり「真ん中~下」にメインの緊張がある人が発症しやすいのではないかと感じる。
予後について
「アレルギー性紫斑病」「血小板減少性紫斑病」において共に難しいのは、
「今の状態が、真の回復に向かっているのかどうか」
と、いう見極めであろう。
症状が収まっても、時間を置いて紫斑病が再発症してくるケースは、「ストレス・飲食・筋緊張・内臓への負担」などの根本原因が解消されていないからである。
お子さんなら成長するにつれ、内臓の処理能力が上がり再発しにくくなるケースもあるだろうが、環境によっては成人になってから発症する人もいるのは体内環境の乱れや負担などがあるからだ。
紫斑病の回復過程において、いつかはクスリを減らしていく必要が出てくる。
もちろんステロイドは急に切ると危ないのだが、かといって、長期服用は副作用のリスクが高まる。
まずはドクターと患者さんの話し合いのもと、回復状態を見て徐々に減らしていく事が基本線となる。
我々のところに来られるアレルギー性紫斑病の方は、病院でのステロイドを服用した状態で、
「症状(紫斑・腹痛など)が大きく進展しないので回復したい」
と、願われて来られる方が多い。
血小板減少性紫斑病の場合もまた、ドクターと患者さんが話し合ってステロイド服用のコントロールをされているケースが多いと思われる。
そして、ドクターは症状(紫斑など)を考慮しつつ、最終的には検査数値を判断基準にして、今後の方針を決めていく事になるだろう。
だが、たとえ症状がマシになったとしても、数値が悪いままだと、ドクターはクスリを減らしていく事に対し慎重になるはずだ。
ただ、クスリを減らさないと内臓の回復力は上がってこないため、回復が遅くなるし、何より長期服用は体にとっても良くない。
血小板減少性紫斑病において、紫斑などの症状が改善している場合でも、血小板の数値は依然として良くないケースがある。
こうした場合、2ヶ月位のタイムラグを経て、数値も上がっていく傾向があるようだ。
体の回復力が上がり、症状は改善されていても、なぜか数値がついてこないのは、「体の反応」である以上、明確な答えは分からない。
(そもそも西洋医学的に原因が特定できているわけでもなく、もしかすると血小板減少だけの問題ではないのかもしれない。)
アレルギー性紫斑病では血小板数に関係なく血が漏れるのだから、体の回復さえ進めば出血はある程度と止まってくるのかもしれず、回復にあたり体が血小板を新たに作るとしても、大幅に減少していたものがすぐに解決するわけではないだろうし、徐々に数値も戻ってくる方が自然といえば自然な形なのかもしれない。
しかし、病院ではどうしても数値を基準にしてしまうため、
「症状はマシになっているが、血小板数値が低いので、慎重に様子を見よう」
と、なってしまいやすく、結果として、クスリの服用期間が長くなり、治癒力が上がってこず、回復が遅れる事になってしまう。
(6ヶ月を越えて慢性型に陥ってしまう一つの側面としてこういう流れもあるのではないか?)
仮に、症状や体調が改善してきているタイミングで、クスリも上手く減らしていく事ができれば、回復力は上がっていきやすくなるだろう。
「出血症状そのものが改善していない」ならば、数値とリンクするので慎重にならざるを得ないのも致し方ないが、
「出血症状が改善しているが数値がついてきていない」のは、タイムラグが生じているだけかもしれない。
確かに、数値が低いのに症状・体調がマシになっているのは一見矛盾しているように思えるが、体というものは、数値や検査結果だけで全てが分かるわけではないし、数値も検査のタイミングで変わる事もあるのだ。
数値は数値で確認は必要だが、そこに捉われ続けると本質を見逃してしまうのではないか。
もし、無痛整体や漢方などのサポートを受ける事で、体の自然治癒力が引き出され、紫斑がマシになっているのならば、数値が低くても今の状態はいい傾向だといえる。
この場合、クスリを減らしても体の回復力は上がっているので、体の回復と共に2ヶ月位のタイムラグを経て数値も落ち着いてくる可能性は高いと思う。もちろん、様子をみて体の調整はし続けながらであるが。
根本原因の生活背景や筋緊張・自律神経・内臓の安定を解消するのだから、再発を防ぐ可能性も高いだろう。(本人の今後の生活スタイルも影響する。)
だが、クスリで症状を抑える処置のみを行い様子をみていた場合、体がそれで徐々に回復してくれれば良いが、長期のクスリ・安静・ストレスで体が回復していない、あるいは老廃物処理が進んでいないのならば、なかなか状態が上向いていきにくいかもしれない。
原因(筋緊張・自律神経・老廃物)が解消されていないし、解消するための回復力も落ちているからだ。
医療に頼らず自然回復を期待するのも、何かの手助けを得て回復力を高めようとするのも、選ぶのは患者さんである。
ただ、強調しておきたいのは、
「あくまでも無痛整体をはじめとする代替医療は、紫斑病などの病が治る事を100%保証するものではない」
と、いう点である。
◎いくら代替医療を受け続けても、日常生活の乱れに取り組まなければ回復力は上がってきづらい。
◎あまりに状態が悪くなり過ぎてから慌てて施術を受けても間に合わないケース(アレルギー性紫斑病なら腎臓にまで問題が生じてしまう。血小板減少性紫斑病なら血小板の数値が下がりすぎて出血リスクが危険なレベルになる)もあり得るから。
代替医療の立場は、あくまでも患者さん自身の生活環境の見直しを前提とした上で、
「自律神経を介し心身をリラックスさせたり、筋緊張を緩めたりしていく中で、結果として内臓の働きにも影響を与え、回復力向上の可能性を高める」
と、いうスタンスを以て、きっかけを与えていく立場に過ぎないのだ。
そういった理由で、たとえ回復した実績が存在していようとも、
「代替医療を受ければ100%治る」
などとは言えないし、言う方がよほど不誠実だと私は思う。
※補足
個人的に、クスリやワクチンなどの害により、紫斑病が発症するケースが多いように感じている。
クスリの本質は毒であり、副作用というものは毒の本質そのものなのだ。
事実、インフルエンザワクチンなどの副作用群を見ると、紫斑病が含まれている。
背景について詳しくは拙著『現代医療の光と影2』を参照してほしい。
この記事に関する関連記事
- アレルギー性紫斑病が改善(潰瘍性大腸炎→腎臓ガン→クローン病→アレルギー性紫斑病) 大阪府 Sさん 40代 女性
- アレルギー性紫斑病や血小板減少性紫斑病が新型コロナワクチン接種後に増加している
- アレルギー性紫斑病が改善 大阪府 Mさん 28歳 女性
- アレルギー性紫斑病が改善 大阪府 Hさん 2歳 女性
- アレルギー性紫斑病が改善する理由 大阪府羽曳野市の治療院「逍遥堂」
- 私が東洋医学に興味を持ったいきさつ
- 新型コロナワクチン後遺症 ファイザーが公開した1291種類の副作用
- 【動画】アレルギー性紫斑病に数多くの回復実績! 自然治癒力を引き出す無痛整体 小さなお子さんへの施術風景
- 「ワクチンが感染症を減らしてきた」という嘘
- 動くとすぐ紫斑が出るアレルギー性紫斑病が改善 大阪府 Sさん 20代 女性
- 手足の紫斑、ふくらはぎの痛み、吐き気を伴うアレルギー性紫斑病が改善 大阪府 Yさん 5歳 男性
- アレルギー性紫斑病の原因と改善方法
- ワクチン・薬の副作用でアレルギー性紫斑病が多発
- 手足にたくさんの紫斑!アレルギー性紫斑病が改善 奈良県 Sさん 5歳 女性


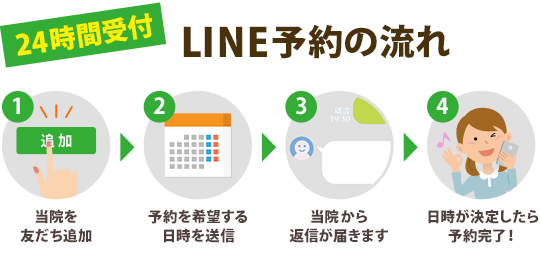
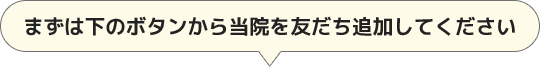


お電話ありがとうございます、
逍遥堂でございます。